|
それは、果たして、インクの性能に起因する正当な価格差なのであろうか。
ここで、インクの成分を考えてみたい。
ご承知のように、インクの成分は企業秘密の部分が多く、正確な成分は知ることができない。しかしながら、MSDS(製品安全データシート)を参照することによって、大まかな成分は知ることができる。(興味のある方は、以下のURLを参照してほしい。
http://cweb.canon.jp/ecology/products/msds/ij/index.html
BCI-7eYでは、以下のようになっている。
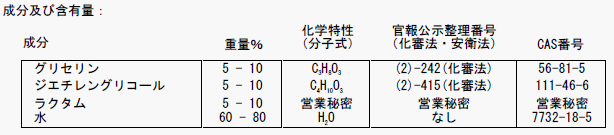
同じ7eシリーズでも、マゼンタでは以下のようになる。
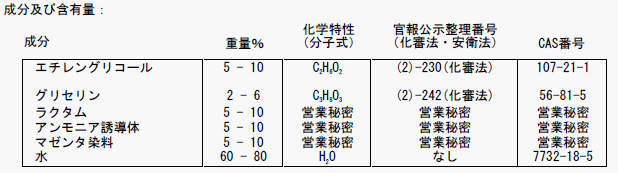
また、ブラックでは、
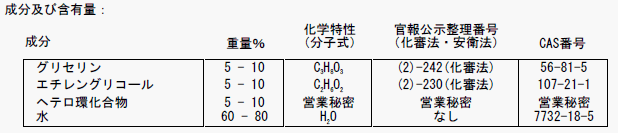
フォトシアンでは、
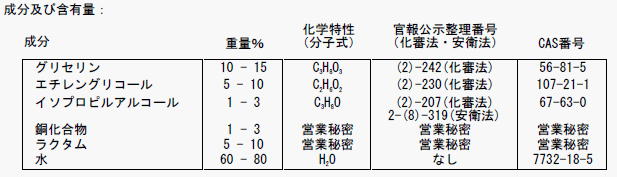
というように、色の違いによって、成分も大きく変化しているのである。
インクの性質は、成分だけでは語れないものであり、インクの持つ、耐光性、耐ガス性、発色性能、ヘッド内での耐熱性、防錆性能、防腐性などを高度にクリアしている必要があるはずである。
ここで、中島 一浩氏(キヤノン インクジェット技術開発センター)による、記事を紹介したい。
氏によれば、サーマル式のプリンタが、ヘッドからインクを射出するのは、我々が想像するような、気泡がインクを押し出すような生やさしいものではなく、
「高温に熱した鉄板の上に水滴を落とすと,水滴が激しくはじけ飛ぶのは誰しもご存知だと思う。このはじき飛ばす力がサーマルの原動力「膜沸騰」である。高温の壁に接した瞬間の水は全体が沸騰することはなく,壁に接したごく一部の水だけが瞬間的に気化する。こうした現象は100℃程度では起こらない。例えば水の場合は,約300℃以上が必要である。この温度を過熱限界温度と呼ぶ。
膜沸騰現象で発生する圧力はきわめて大きい。水の場合では約100気圧にも達する。火山活動で時折「水蒸気爆発」という言葉を耳にすることがあるが,これもまた地下水がマグマに触れて起こった膜沸騰現象である。大きな山の形を変えるほどの高圧をノズルの中に閉じ込めて,小さなヒーターで正確に制御するのがサーマルの基本原理なのである。」
というくらいの、過酷さがあるとのことである。また、この加熱によるインクの焦げや消泡時の衝撃も開発時の障害であったようである。
「次なる壁が,Kogationである。この単語は,英語にしてはちょっと変だと思われるかもしれない。実は日本語の“コゲ”からできた言葉である。今では,れっきとした国際的に通用する技術用語となっている。文字通り,ヒーター上にできるいわゆるコゲの問題を指している。
サーマル開発の当初,ヒーター上にすぐにコゲが発生し,インクはあっという間に飛び出さなくなってしまった。ヒーターの表面は,瞬間的には数百℃に達する。高温にさらされるのはわずか100万分の1秒程度ではあるが,コゲは少しずつ堆積していく。数百万回繰り返されると,貯まり貯まったコゲで熱が伝わらなくなってしまうのであった。
最初は,いったい何が焦げるのかすらよく分かっていなかった。やがてインクの中に含まれるいくつかの不純物がコゲを発生させていたことが突き止められた。
泡消滅時の圧力でヒーターが破損
残る課題はCavitationである。泡が消滅する際に強い衝撃が発生する現象のことである。
先に述べたように,サーマルでノズル内に発生した泡は,気化直後は100気圧近い高圧を発生する。しかしわずか100万分の1秒後には,泡の内部はほぼ真空状態になる。この真空の泡は,10万分の1〜2秒程度というわずかな時間で押し潰されて消滅する。この瞬間非常に強い衝撃が発生し,ヒーターの表面に穴が開いて破壊してしまう。
タンカーなどの巨大船のスクリューでも,設計が良くないとあっという間に羽根が折れてしまうそうである。これも実はCavitationの仕業である。スクリューが回転する場合,羽根の上流側のスクリュー表面近傍は急速に減圧される。すると水中に無数のほぼ真空の気泡が生まれ,すぐに消滅する。この消滅の瞬間に発生するCavitationによって,スクリューの羽根は破壊されてしまうのである。
このように,Cavitationは硬い金属をも破壊するほどのすさまじい破壊力を持つ。ヒーター表面の材料を徹底的に追究することで強度を高めた。さらに衝撃自体を緩和する流体力学設計を施すことで問題を克服し,今日に至っている。」
これらの引用文は、以下のURLで全文が読めるので、参考にしてほしい。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070613/274584/?ST=ittrend
こうしてみると、この過酷な状況で使用されるインクには、ミクロの世界で先進の技術が詰め込まれており、そうして開発されたインクが、ちょっとやそっとでまねできないものであることは容易に想像できる。
その対価としてインクの価格が設定されているならば、正当な価格であると評価できるかも知れない。
それにしても、高い…
|